ソーシャルレンディングは危険?リスクと問題点のまとめ、もし業者が倒産したら…
執筆者:川原裕也
※記事内に広告を含む場合があります
当サイトは更新を終了しました。
長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。
※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
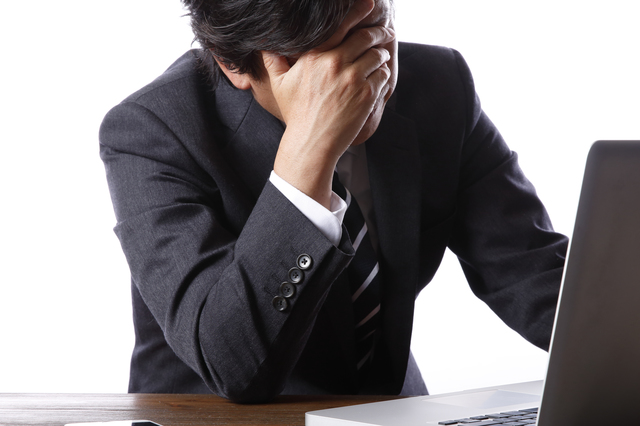
ソーシャルレンディングには、あまり知られていない問題点やリスクがあります。
例えば、もしソーシャルレンディング業者が倒産したらどうなるのか?など、多くの投資家が周知していないリスクもたくさんあると思います。
今回は、ソーシャルレンディング投資をする中で気になった問題点についてまとめたいと思います。
目次
ソーシャルレンディングが抱えるリスクと問題点

ソーシャルレンディングには、貸付先のデフォルト(貸し倒れ)による元本割れリスクがあります。ハイリスクな投資商品である点に注意が必要です。
しかし一方で、
- 投資家は自分自身で投資する案件を決められる
- 小口に分けて分散投資することで、1案件の投資額を小さくできる
という2つの自由があるため、厳格な投資判断を下していくことで、安全に運用することができます。
1つの高利回り案件に大きく投資するよりも、「自分が貸金業者をビジネスとしてやっている」というような感覚で、出来る限り投資先を分散することが、ソーシャルレンディング攻略のコツだと私は考えています。
ソーシャルレンディング業者が倒産した場合

ソーシャルレンディングに投資する上で、最も気をつけたいのは「業者自身が倒産してしまう」可能性です。
- 投資家に対する説明が不透明
- 新規の募集案件が停止している
- なんとなく怪しい
このようなソーシャルレンディング業者には、資金を投じるべきではないですし、そのような会社からは早めに出金しておくことをおすすめします。
基本的に、ソーシャルレンディング業者は、顧客資産を分別管理しているのが普通です。
つまり、万が一業者が業績不振で倒産しても、分別管理されている顧客資産には一切ダメージがないという仕組みです。
しかし、中には分別管理しているといいながら、その仕組みが甘くなっている業者が存在する可能性も考えられます。
この部分については、投資家保護の観点から見てもとても重要となるため、これから徐々に透明化されていくことが予想されます。
個人的には、大手で信頼できるソーシャルレンディング業者を除いて、大きな資金を預けるのはリスクが高いように思います。
投資案件の倒産リスクならまだしも、業者の倒産リスクまで負わされるというのは、正直怖いです。(最も、銀行が倒産した場合も、1,000万円以上の預金は保証されませんので、預金者が倒産リスクを負っていると言えますが)
こうした理由から、私は基本的に12ヶ月以内の短期の投資案件に厳選して投資するようにしています。
将来的に、業者の倒産によって投資家が被るリスクが軽減される仕組みとなれば、より積極的にソーシャルレンディングへ投資できるかと思います。

あわせて読みたい:
(怪しい業者も含む)ソーシャルレンディング業者を案件や手数料で比較
貸付先の倒産リスク

ソーシャルレンディングはあくまでも投資なので、元本保証ではありません。
貸付先が破綻し、貸したお金が回収できない場合は投資資金を毀損する可能性があります。
こうしたソーシャルレンディングのリスクは、投資資金を小分けにして複数のプロジェクトに分散投資することで解決できます。
例えば、300万円の投資資金を利回り10%で運用した場合、年間リターンは30万円です。この場合、300万円を1つのプロジェクトに投資するのではなく、10万円を30件のプロジェクトに小分けにして投資をします。
そうすると、もし1年で1件の貸し倒れに直面しても、年間リターンは20万円(利回りは6.66%)を確保することができます。
ソーシャルレンディングの投資案件の一部には、「担保・保証」がついています。担保・保証があれば、万が一返済遅延が起きても、最悪の場合、担保を売却することで資金を回収することが可能です。
しかし、担保には「抵当権の順位」があり、順位が低い場合は、返済遅延の時に担保相当額の回収が難しくなるケースが少なくありません。
また、不動産担保の場合、不動産の価値が目減りしていると、担保を売却しても当初設定した金額にならず、全額回収が難しくなる場合もあります。
担保付き案件を狙うのであれば、オーナーズブックのような、担保評価額が融資金額以上の評価となっている案件を選ぶのがおすすめです。
- 貸付先を分散する
- 貸付先と担保の質を厳選する
これらはいずれも、ソーシャルレンディング投資を成功させる上で必要不可欠です。
投資先が不透明

ソーシャルレンディングには、「貸付先の社名などの詳細を開示できない」というルールがあります。
こうした理由から、案件の詳細が「貸付先:A社(都内で不動産運営を行っている会社)」のような「ぼかした説明」になっていることが多いです。
業界大手のmaneo(マネオ)のように、開示できる範囲で出来る限り詳細な情報を提供してくれている、良心的なソーシャルレンディング業者もあります。
しかし、貸付先がわからない以上、貸付先の信用はソーシャルレンディング業者の調査力を信じるしかないのが現状です。
万が一、貸付先が債務超過に陥っていて、自転車操業状態にあっても、その詳しい業績は投資家には伝えられません。
業者は厳格に募集案件の審査を行っています。(それがソーシャルレンディング業者の信用を築く上で重要になるからです)
しかし、現在の不透明な状況でただ「業者の審査を信じる」というのは、投資家としてリスクが大きすぎると私は考えています。
業者が審査ミスをし、問題のある投資案件が募集された場合でも、「危険な案件を避ける、質の高い担保がある案件を選ぶ、損失を最小にするために分散する」という投資家ができる最大限のリスクヘッジをしておくことが大切です。
これから詐欺のような業者が出て来る可能性がある

これは、近い将来起こるだろうと私が予想しているリスクです。
昨今、多数のソーシャルレンディング業者が乱立している状態にあります。
その中には、本当に信頼できる業者なのかどうか怪しいと思える会社も存在しますし、こうした状況はこれからも当面は続くと思われます。
例えば、年利18%の高利回りプロジェクトを連発しているソーシャルレンディング業者が登場したらどうでしょうか?
数あるソーシャルレンディングの中でも、利回り18%というのは異例です。
しかし、投資詐欺から身を守る方法という特集ページの「ポンジ・スキームとは?投資詐欺で使われる典型的な仕組みを理解する」という記事でも書いたように、考え方によっては、高い利回りで投資家の資金を集めて短期間で計画破綻してしまうことを狙っている業者があるかもしれません。
ポンジ・スキームとは、顧客から集めたお金を実際には融資せずにそのまま配当として還元し、高利回りを演出する詐欺の手法です。
前述のとおり、ソーシャルレンディング業者が倒産した場合はその預かり資産が返還されないリスクがあります。
このように考えると、やはり利回りが低くても本当に信頼できる業者に絞って投資をするのが安全な道だろうと私は思います。
では、どのような業者が信頼できるのかというと、最大の見分け方は「大手からの出資を受けている」かどうかです。
クラウドクレジット
国内大手の総合商社「伊藤忠商事」やマネックスグループのベンチャーキャピタルが出資。
クラウドリアルティ
SBIグループのベンチャーキャピタル「FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合」が出資。(左記ファンドには、ソフトバンクやみずほフィナンシャルグループなど大手企業が出資)
オーナーズブック
不動産クラウドファンディングに特化。上場企業のロードスターキャピタルが運営。
上記のソーシャルレンディング業者は、安心できる業者であり、少なくとも詐欺業者の可能性はありません。
途中解約ができない

ソーシャルレンディングは原則として途中解約ができません。
これは問題点というよりも、商品特性上のリスクです。一方で、ソーシャルレンディングは償還期限(返済期限)があらかじめ決まっているので、期間限定で運用したい場合に向いています。
例えば、3ヶ月後に必要になるものの、現在は使い道がないお金は、償還期限が3ヶ月のソーシャルレンディングで運用することで、効率よく資産運用ができます。
課題は多いが時間が解決
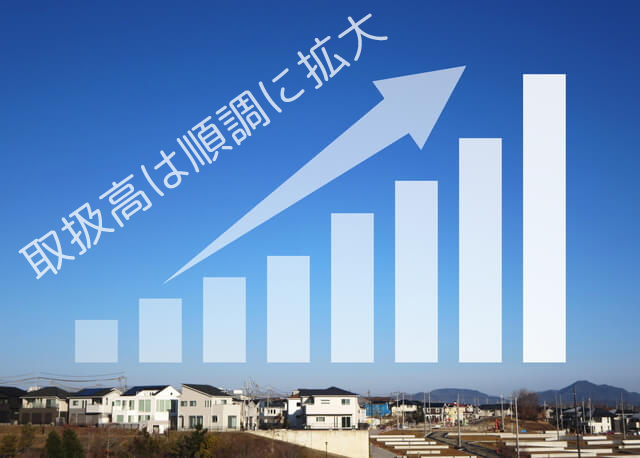
「フィンテック」が注目されている中で、GMOクリック証券が業界大手のmaneo(マネオ)と提携し、自社でソーシャルレンディング案件を取扱うなど、貸付型クラウドファンディングは今後ますます盛り上がりを見せるようになると思います。
現在は、怪しい業者が存在したり不透明な部分が存在するといった問題点もあり、将来的に1つか2つくらいは大きな事件も起こる可能性はあると考えています。(実際、今となっては一般的な投資先となったFXも、黎明期には数多くの問題があった)
とはいえ、悪質な業者の淘汰、業界全体での情報開示の透明化はこれからさらに進んでいくと考えます。
魅力的な投資先のひとつになると思いますので、貸し倒れを避けて安定的な利回りを目指しましょう。
1億人の投資術「ソーシャルレンディングの教科書」では、これからもソーシャルレンディングに関するさまざまな情報を提供していきます。
次の記事は、「ソーシャルレンディングは詐欺ではない。が貸し倒れのリスクは小さくない」です。

ソーシャルレンディング関連記事
最後まで読んでいただきありがとうございました
こちらの記事にコメントが投稿されました
-
P さんがコメントしました - 2023年12月18日
決算書の「百万円」や「千円」の単位を素早く読む方法 -
No Name さんがコメントしました - 2023年10月8日
プロスペクト理論とは?投資に活かす方法、あなたの知らない心理学の世界 -
DCF法くん さんがコメントしました - 2023年8月21日
DCF法の世界一わかりやすい解説、割引率の決め方やエクセルでの計算方法 -
No Name さんがコメントしました - 2023年8月19日
DCF法シミュレーター -
にゃん太郎は長生き さんがコメントしました - 2023年6月19日
証券マンがおすすめするファンドラップの評判を信じて買って良いのか
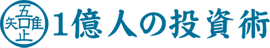
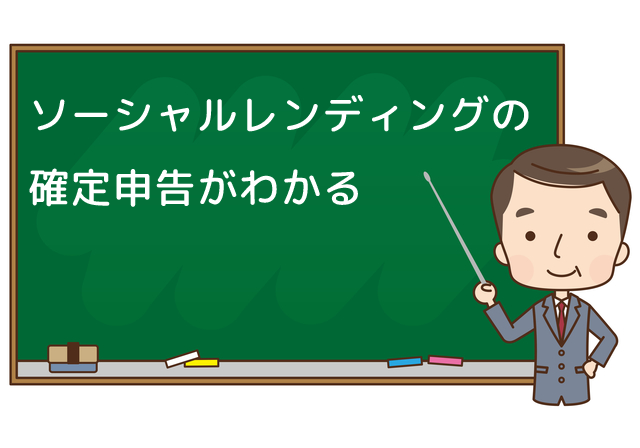



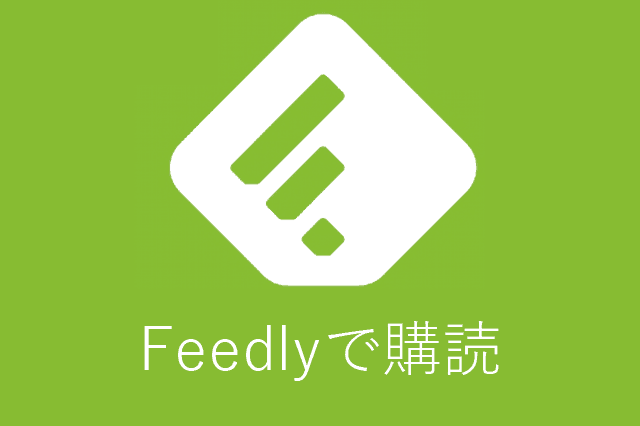
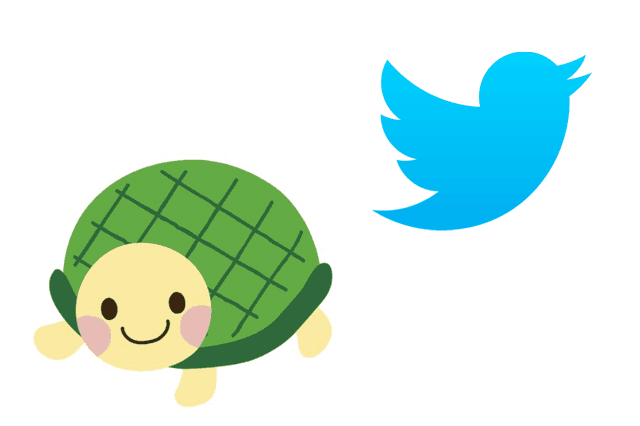
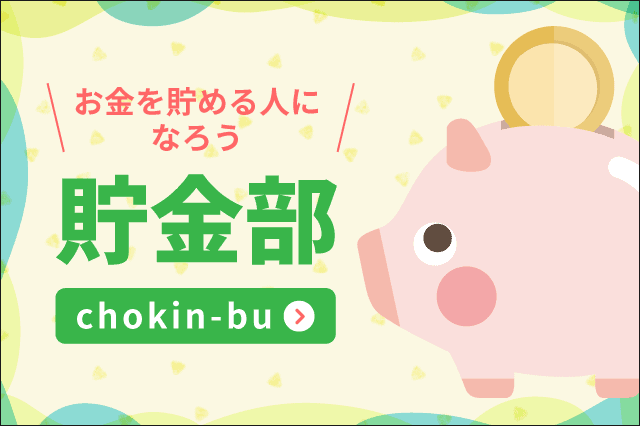



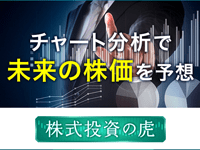
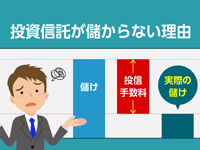

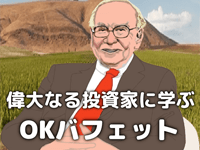

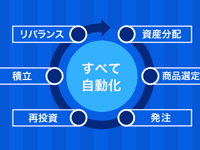

0件のコメント