投資で法人化!資産運用会社を設立するメリット・デメリットまとめ
執筆者:川原裕也
※記事内に広告を含む場合があります
当サイトは更新を終了しました。
長きにわたり当サイトを愛読、応援くださった方々には誠に感謝しております。
※この記事の内容は執筆時点のものです。サービス内容・料金など、現時点の最新情報とは異なる場合がございます。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

一部の証券会社やFX業者では、法人口座が開設できます。
法人口座はもちろん、法人でなければ作ることができないのですが、最近は会社設立が容易になったことから、個人で「資産運用会社」を作り、法人口座で取引する人も出てきています。
今回は、株式投資やFXをする個人投資家が、個人で資産運用会社を設立するメリット・デメリットについてまとめます。
ここで言う「資産運用会社」とは、特定の資格を有した機関投資家ではなく、個人が資産運用のためだけに会社を作ること(いわゆる資産管理会社)を意味しています。
目次
主なメリット
個人投資家が資産管理会社を設立する場合、主に税制面のメリットが大きいです。
損益通算できる

資産運用会社を設立する最大のメリットは、あらゆる金融商品の取引を損益通算できることです。
個人の場合、
- 会社からもらった給与所得
- 株で稼いだ損益(株式等の譲渡所得)
- FXや先物で稼いだ損益(先物取引に係る雑所得等)
などはそれぞれ別の扱いとなるため、損益通算はできません。
例えば、株やFXで損失を出しても給与所得の税金は払わなくてはなりません。
FXと先物は「雑所得」として損益通算できますので、先物で損失を出しFXで利益を上げた場合は、FXの利益と先物の損失を相殺して税金を減らせます。
しかし、株式とFXは損益通算できないので、FXで利益を出し株式で損失を出してしまった場合でも、FXの利益で発生した税金を減らすことはできません。
一方で、法人口座であれば損益はすべて合算できます。
- 会社の事業で発生した損益
- 株で稼いだ損益
- FXや先物での損益
などすべての損益をまとめて、「法人の利益」として申告することが可能です。
最大7年間、損失の繰越ができる

もし、株式やFXの取引で損失が出てしまった場合でも、法人であれば最大7年間は損失を繰り越せます。
つまり、今年300万円の損失を計上しても、7年以内に300万円の利益をあげて取り返せば、過去の損失と相殺できるため、300万円の利益にかかる税金は0円となります。
損失の繰越は個人でも可能なのですが、最大3年に限定されているため、繰越可能な年数が長い法人にメリットがあると言えます。
また、2018年1月時点のビットコイン(仮想通貨)投資のように、一部の投資商品は個人では雑所得扱いとなり、損失の繰越ができないことがあります。
しかし、法人であればビットコインでもFXでも、どのような投資商品でも事業損益と合算できるため、会社が赤字になれば、その赤字について最大7年間の損失繰越ができます。
FX法人口座におけるレバレッジ規制

FX(外国為替証拠金取引)では、投資家保護の観点からレバレッジ規制が行われており、現在個人投資家は最大25倍までのレバレッジしか利用できません。
一方で、FX法人口座にはレバレッジ規制がなかったのですが、2015年にスイスフランが急変動を起こしたことがきっかけで、法人口座においても、巨額の未回収が発生(FX業者が顧客の損失を回収できなかった)したため、現在は規制の対象となっています。
法人口座のレバレッジ規制については、FX業者によって異なるのですが、最大25倍としているところや、最大100倍にしているところもあります。
例えば、「外貨ex byGMO」ではレバレッジの上限値を公表しています。
上記を見る限り、概ね60倍程度が法人口座の最大レバレッジになりそうです。(記事執筆時点の情報)
以前に比べるとレバレッジ規制が進んではいるものの、個人口座よりもレバレッジをかけやすいことも、資産運用会社を設立するメリットです。
節税メリットが大きい

単純に、事業に関する費用を経費として計上できるため節税につながります。
例えば、株式取引に関する本を買ったり、FXのセミナーに参加したりする場合、それらの費用を全額経費として扱えるのが法人の強みです。
その他、退職所得や相続に関する点でも節税メリットが大きいのが法人の特徴です。
もっとも、つみたてNISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)のように、個人でしか利用できない節税効果の高い制度もたくさん存在します。
こうした仕組みを活用できるのは、法人にはない個人ならではの強みです。
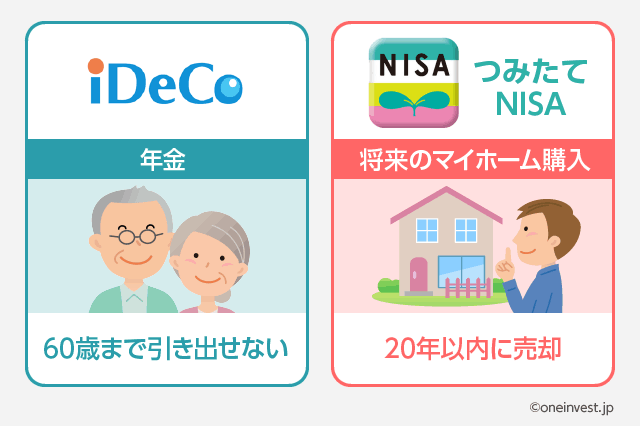
あわせて読みたい:
つみたてNISAとiDeCoはどっちを選べばよい?違いとメリット・デメリット
株主優待の2重取りができる
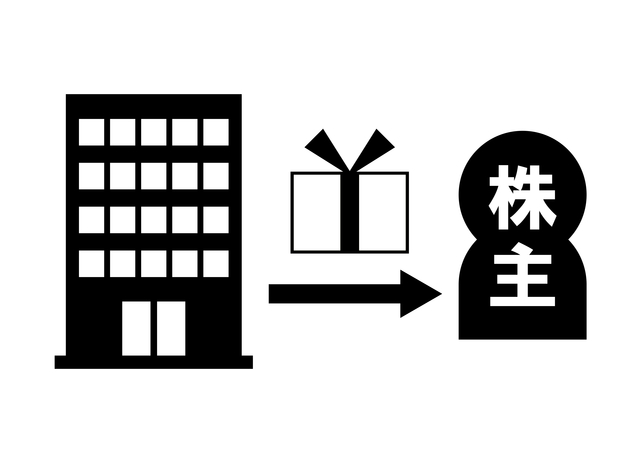
「個人」と「法人」の両方で株式を保有すれば、株主優待が美味しい会社から2倍の優待を取得できます。
例えば、カゴメ(2811)の株主優待は、
| 保有株数 | 株主優待の内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 1,000円相当の自社商品 |
| 1,000株以上 | 3,000円相当の自社商品 |
となっています。
カゴメの株式を1,000株以上保有しても、それ以上優待は増えません。しかし、個人口座と法人口座でそれぞれカゴメ株を1,000株保有すると、それぞれの口座で株主優待がもらえるため、合計6,000円相当の自社商品を手に入れることができます。
これは、資産管理会社を設立する隠れたメリットの一つです。
個人口座と法人口座を別で開設できる

「法人」は別人格ですから、1つの証券会社で個人口座と法人口座の両方を持つことができます。
この時にメリットとなるのが、IPO投資の抽選です。
証券会社によっては、IPO(新規公開株式)の割当を抽選としていることが少なくありません。
本来、個人は1つの証券会社に1つしか口座を作れないので、抽選への参加も1口のみとなります。
しかし、資産運用会社を作ることで、1つの証券会社に「個人口座」と「法人口座」を作ることができるため、その両方でIPO株の当選チャンスを得ることができます。

あわせて読みたい:
IPO(新規公開株)で稼ぐ、証券会社ごとの抽選方式を比較
主なデメリット
利益が出た時の税率が高い

資産運用会社設立の大きなデメリットに、利益が出た時の税率が高いことがあげられます。
株式投資やFXの場合、個人であれば(復興所得税を含め)利益に対して約20%が課税されます。
しかし、近年下がりつつあるとは言え、法人の実効税率は約30%です。
つまり、継続的に利益を出し続けるのであれば、手元に残る資金は個人の方が多くなるため、税制面や複利効果を考えると個人で取引した方がお得です。
一方で、法人の場合は節税メリットが大きいのが強みです。
事業に関する一部の出費を経費として計上したり、役員報酬を自分に対して支払うことで会社から個人に支払う給与を経費にすることができます。
また、想定外の損失を被ってしまった場合でも、7年間の損失繰越ができます。(個人の場合は最大3年)
利益が出る限り支払う税金は多くなるものの、損失発生時には法人の方が強みがある、ここが資産運用会社を設立するかどうかの悩みどころです。
費用負担が増える

資産運用会社を設立すると、単純に費用負担が増えます。
会社設立時に約30万円程度が必要になりますが、その後も最低でも維持費として毎年7万円ぐらいかかります。(住民税の均等割など)
また、法人は決算申告の必要がありますが、決算の手続きが煩雑なため税理士に依頼をする必要性があり、簡単な資産運用会社の決算でも年間10万円~50万円程度の税理士報酬は必要になってきます。
社会保険についても、会社が半額を負担しなくてはならないといったデメリットがありますが、この点については個人で管理する資産運用会社であれば大きな問題ではありません。
やはり、税理士報酬などの法人の維持にかかる費用が最も大きなデメリットだと思います。
FXの評価損益が課税対象になる
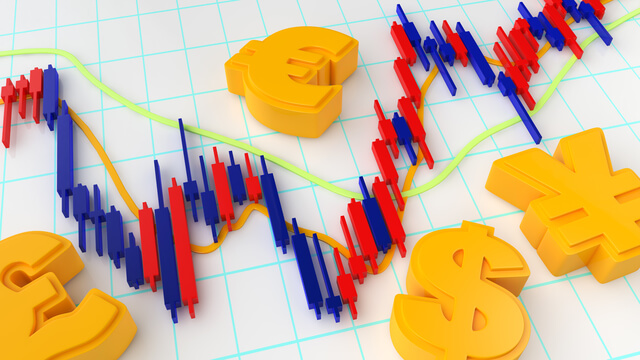
個人の場合、株式やFXは売却して利益を確定しない限り課税されることはありません。含み損益に対しては税金は発生しません。
しかし、法人の場合はFXに関しては評価損益(含み損益)が課税対象となります。
株式は、簿価計上が可能なので個人と同じ扱いにできますが、FXについては含み損益が発生していると、その含み損益を決算時に利益(または損失)として算出し、その分の税金を支払わなくてはなりません。
※含み損が発生している場合は売却しないまま損失計上できるため、節税になります
結論

個人で投資をするのと資産運用会社を設立するのでは一長一短があるため、どちらが決定的に良いとは言えません。
資産運用会社を設立すべきかどうかの判断としては、「法人の設立や維持にかかる費用が気になる」というレベルであれば引き続き個人で投資をした方が良いかと思います。
逆に、設立費用や維持費用はまったく気にならないが、「税金があまりに高いので節税メリットを享受したい」と感じる人であれば、ある程度の資産規模がある状態でしょうから、投資用に法人を設立しても良いと思います。
また、個人の場合は「つみたてNISA」や「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」といった、国が主導して提供している節税策があります。
つみたてNISAの場合は年間40万円、イデコの場合はサラリーマンなら年間最大276,000円(自営業なら年間最大816,000円)の投資が行え、これらの利益は非課税となります。
両者を合わせると毎年100万円近くの非課税投資が行えるので、まずはつみたてNISAやイデコのような個人が扱える「枠」を使い切り、法人化はそれから考えても遅くはないと思います。
また、法人化の後に余剰資金の運用を考える場合は、「中小企業の社長が考えたい余剰資金の運用先5選(今日の経営・姉妹サイト)」という記事を参照してください。
一般的な事業法人の利益を資産運用に使う場合、どのような投資先が考えられるかまとめています。
また、姉妹サイトの「今日の経営」では会社設立にあたって必要な情報なども紹介していますので、これから法人化を考えようとしている方はあわせてご覧ください。
▼会社設立freeeを使って自分で簡単に会社設立できます(無料で使えます)
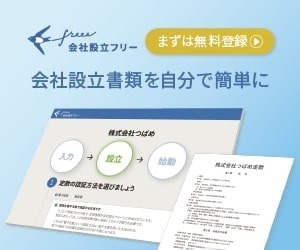

関連リンク
最後まで読んでいただきありがとうございました
こちらの記事にコメントが投稿されました
-
水谷 真逸 さんがコメントしました - 2025年1月16日
マネタリーベース、マネーストック、マネーサプライの違いは?過去推移を調べる方法 -
ゆずっこ さんがコメントしました - 2024年12月2日
ゆうちょ銀行のiDeCo(個人型確定拠出年金)ゆうちょAプランの手数料と評判 -
No Name さんがコメントしました - 2024年11月23日
決算書の「百万円」や「千円」の単位を素早く読む方法 -
P さんがコメントしました - 2023年12月18日
決算書の「百万円」や「千円」の単位を素早く読む方法
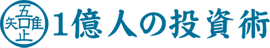

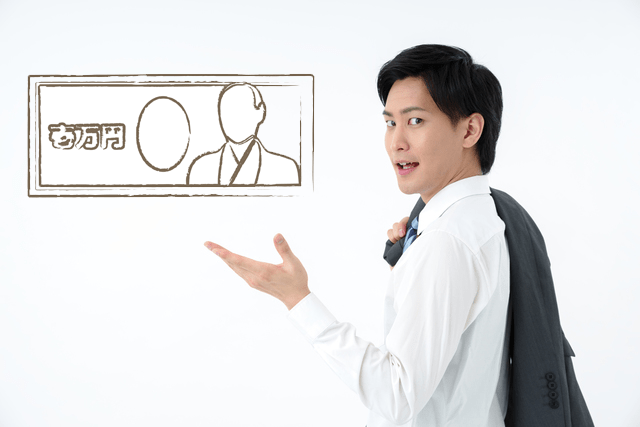
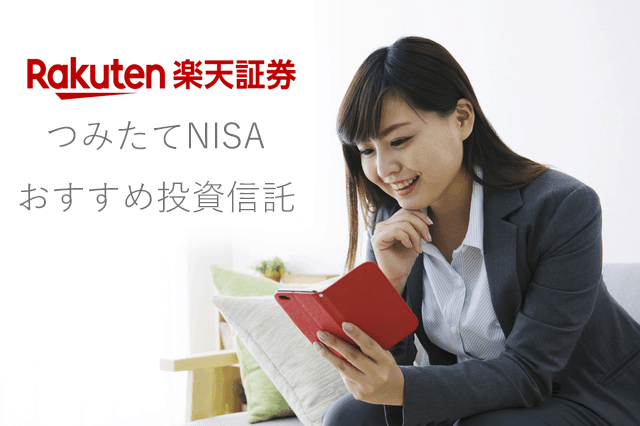



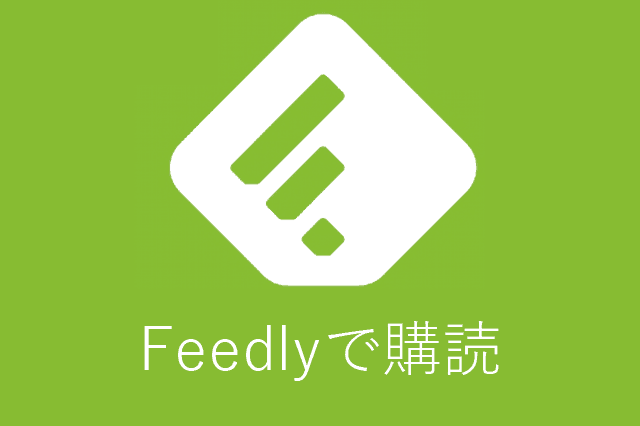
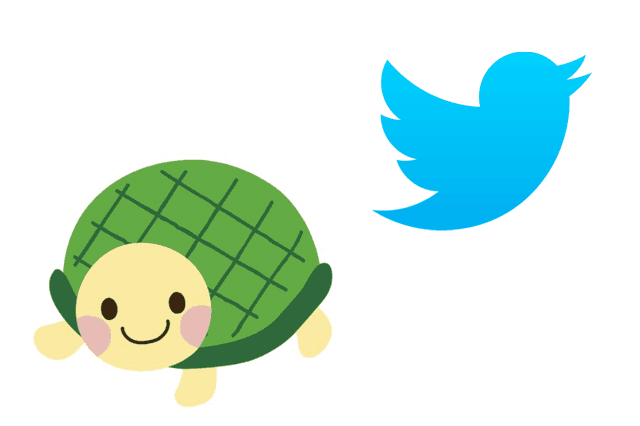
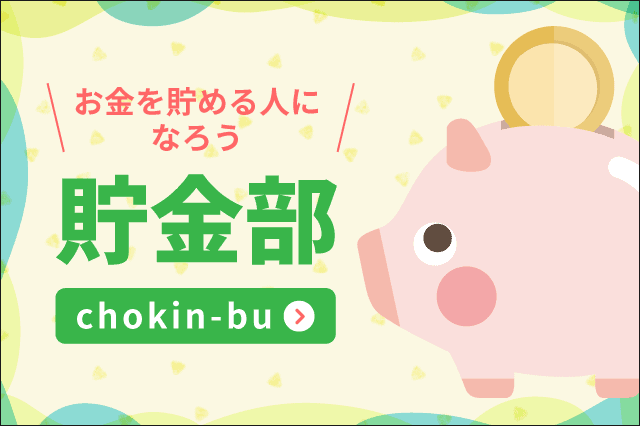



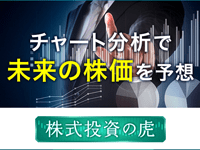
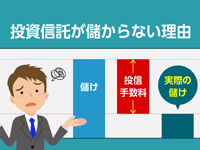

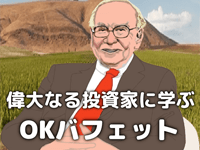

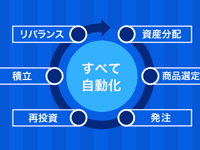

0件のコメント